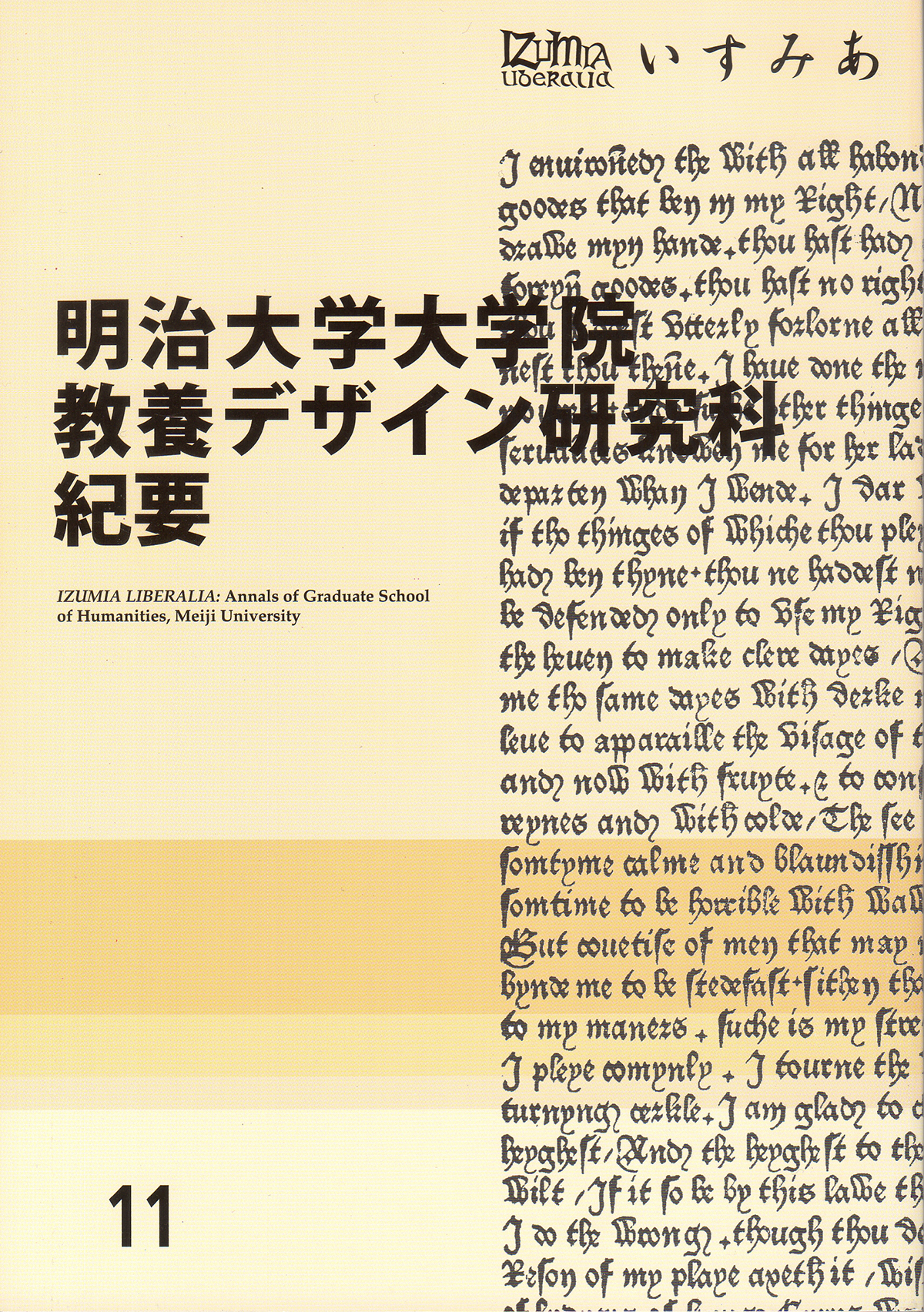丸川哲史さんのお誘いを受け、昨年行われた明治大学大学院教養デザイン研究科主催の特定課題講座「風に吹かれて テントは世界を包む2018」でゴッホや共同体について話をさせていただいた。和泉校舎の中庭に出現したテント劇団「野戦之月」のテントの中で行う講座だ。共同体の話をするには最適な場所でした。
講座の報告として、今年の三月に発行された紀要「いすみあ」に丸川哲史さんが文章を書いてくれていた。その時出会った「野戦之月」の今秋の公演の手伝いも終わり、次のステップに進むために丸川さんの報告をこのブログに掲載したいとお願いしたところ、快諾をいただきましたので、以下に掲載します。
いすみあ 11号(2019・3)【特定課題講座】 上岡誠二講演
「神話と共同体〈プロメテウスとしてのヴァン・ゴッホ〉」
丸川哲史
(本稿は上岡誠二氏による6月12日の講演について、当日配られたレジュメを基本として、その後の上岡氏との遣り取りをも反映させ、丸川が整理したものである。)
炎の画家ゴッホは弟のテオと共に画家組合を構想する。アルルの黄色い家で向日葵を描き、キリストの使徒と同じ十二脚の椅子を用意した。ただ周知の通り、その「共同体」の始まりとなるはずのゴーギャンとの共同生活は破綻し、ゴッホは娼家で客を待つ馴染みの娼婦を女神として、自らの耳を切り落とし、それを「ひとつの太陽」として供えるに至る。
日本で積極的にゴッホを紹介した「白樺」の武者小路実篤は、共同体「新しき村」をひまわりと同じく太陽に向かう名前をもった宮崎県の「日向」に建設している。ゴッホの影響は、日本の思想シーンにおいてもはっきりしてる。その後、日向の新しき村は埼玉県に移転するのだが、百年後の今もその「共同体」は続いている。
また、宮沢賢治は短歌や「春と修羅」でゴッホの糸杉を詠い上げている。そういう経緯を経て、「羅須地人協会」という「共同体」を設立したのであった。ゴッホは自らを「農民画家」と呼んだが、賢治は「われわれはみな農民である」と『農民芸術概論綱要』に書いて、資本主義への隷属から逃れよう、と呼びかけている。実際に、新聞が賢治の活動を紹介すると、協会を社会運動と捉えた警察に賢治は事情聴取を受け、「共同体」は崩壊してしまう。「まずもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばろう」という言葉が遺されている。
またゴッホの精神的系譜に属するのではないかと考えられるのが、バタイユである。バタイユはファシズムに対抗するために、まず社会の中で行動する芸術家(主にシュルレアリストたち)との共同体「コントル・アタック」を立ち上げた。ただ、シュルレアリスト達との共闘はまたたく間に失敗に終わる。すると次に、恋人の提案によって、神のいない宗教「アセファル(無頭人)」をつくり、神を殺す、あるいは神を投棄する供儀を試みる。しかしバタイユ自身が犠牲となるような、無頭人そのものにまでは至らなかった。最後に彼は、開かれた共同体「社会学研究会」を立ち上げ、社会学を生きたものにしようとしたが、戦争が始まりすべては無に帰した。
貧困階級をも取り込んだファシズムは、日本にも影響を与え、陸軍の青年将校たちが政権の腐敗や貧困問題を訴え起こした、「二・二六事件」は神話的事件となったが、この事件が一つの契機となり、日本を「共同体」にする発想の下、軍国主義国家が成立した。さらに敗戦後には、民族主義者の高校生、山口二矢が社会党委員長を壇上で刺殺した後に鑑別所で自殺する、という事件が起きている。壁には「天皇陛下万歳」「七生報国」と歯磨きで落書きされていたそうである。大江健三郎は、多くの人が目の当たりにしたであろうこの事件を題材とした小説『セブンティーン』と『政治少年死す(セブンティーン第二部・完)』を矢継ぎ早に発表したが、事件の神話化を食い止めようとした試みであった、と言えるのではないか。
その一方、ファシズムを「芸術の政治化を企てたもの」だとする三島由紀夫は、愛国の共同体「楯の会」を結成し、「七生報国」と書いた鉢巻をして、自衛隊市谷駐屯地に立てこもり、自衛隊に決起を呼びかけた後に自決する。続けて、介錯をした楯の会学生長森田必勝もその場で切腹し果てた。アセファルでバタイユが行おうとして挫折した儀式「供儀実行者自身が彼の打ちおろす刃にかかって崩れ落ち、生贄とともに身を滅ぼす」を実行したとも思える。実は、この事件のひと月前、最後のインタビューで三島はバタイユからの影響を語っていたのであった。
バタイユはゴッホを「われわれ人間たちの血にまみれた神話」に属しているもの、と言う。「共同体」と神話が同時に立ち上がるのだとしたら、その失敗によってゴッホの耳の神話化が起こり、その瞬間に「共同体」が立ち上がったとも言えないだろうか。バタイユは(選択的)共同体を組織することを断念した後に、「とりわけ共同体の不在について見直し、否定的共同体という考えを強調すること。共同体をもたない人びとの共同体」と書いたメモを残している。
バタイユと並んでよく議論されるJ=L・ナンシーは、著書『無為の共同体』で「バタイユにとって共同体とは何よりもまず、そして最終的に、恋人たちの共同体だった」とする。愛の情動によって作られる共同体は、社会を締め出すのであり、その共同体は恋人たち以外には意味を持たないのだが、「鍵のかけられた寝室」の小島の中の「愛」の濃密さは私たちの「生の表情に活気を取り戻させてくれる」。「恋人たちの共同体」を知り、社会の荒廃を感じ取ったうえで、「共同体の実践」を試み、失敗したとき、その時にしか「共同体を持たない人びとの共同体」は立ち上がってこない、とも言えるのではないか。たとえ失敗に終わるとしても、「共同体」への要請を断念してはならないのだ。
「共同体」は人間の情動によって要請されるのだが、その情動には倫理も道徳もない。人は生きる理由を見つけその生を生き抜くために、他者を必要とし共同体を求めて彷徨う。同質的な社会の中で情動を無力化し、生産とその生産物の消費という閉じた円環の中で、意味のない「有用性」に隷属させられたり、指導者と結びついた情動によって、人間を敵とした戦争へと向かわさせられることもある――そのような情動の流れを、押さえつけるの方向ではなく、多くの人が体験するであろう愛の情動〈恋人たちの共同体〉の方から捉え直し、「一個の人間の総合性」と結びつこうとする共同体を、たとえ「魔法使いの弟子」としてであっても、体験し始めなければならない時が来ているのではないだろうか。わたしたちの情動が軍国の「共同体」へと向かう前に。